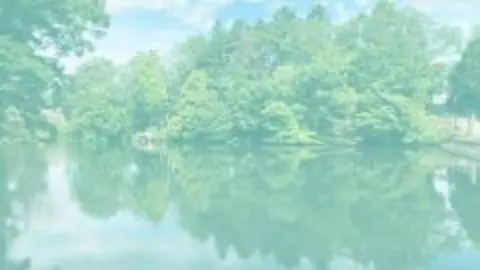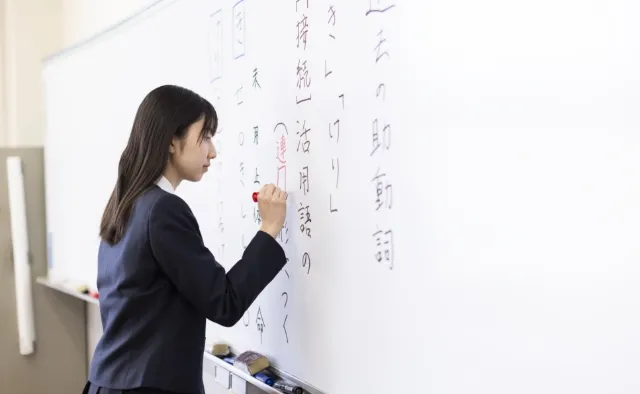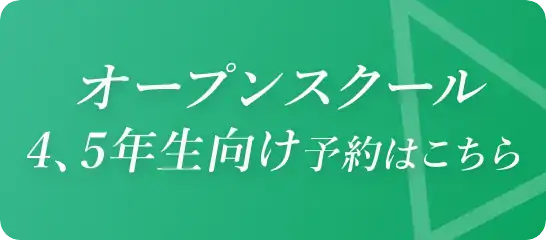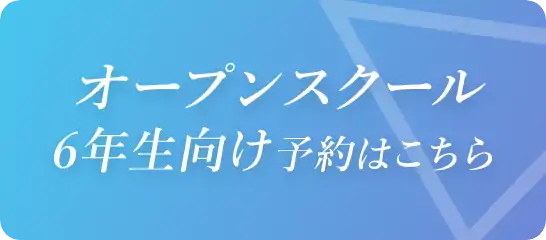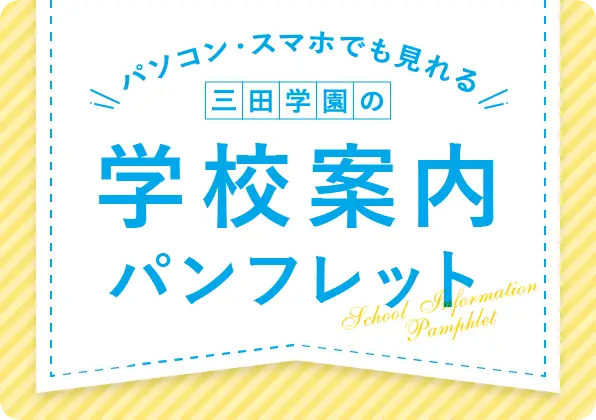お知らせ
-
剣道部
週末は丹有高校総体です
-
中学1年生
中1 道徳をなぜ学ぶのか?
-
生徒会執行部
新入生歓迎プログラム
-
JCA(日本文化研究部), 写真部, 吹奏楽部, 物理部, 美術部, 軽音楽部
5月5日(日)皐月フェスティバル開催
-
生徒会執行部
クラブ紹介
- 全ての記事を見る
-
学園通信
オーストラリア研修 最終日
-
学園通信
オーストラリア研修10日目
-
学園通信
シリコンバレー研修6日目
-
学園通信
オーストラリア研修9日目
-
学園通信
オーストラリア研修8日目
- 全ての記事を見る
-
中学1年生
中1 道徳をなぜ学ぶのか?
-
中学3年生
中3 学力推移調査、SNSについての講演
-
中学1年生
中1 クラブ紹介
-
高校2年生
【高2】新年度2週目終了
-
高校3年生
高3 進路HRと個人面談
- 全ての記事を見る
-
剣道部
週末は丹有高校総体です
-
生徒会執行部
新入生歓迎プログラム
-
JCA(日本文化研究部), 写真部, 吹奏楽部, 物理部, 美術部, 軽音楽部
5月5日(日)皐月フェスティバル開催
-
生徒会執行部
クラブ紹介
-
野球部
大坪杯争奪近隣地区中学校軟式野球大会
- 全ての記事を見る
-
進路指導室だより
共通テストを終えて
-
進路指導室だより
進学希望の既卒の皆さんへ
-
進路指導室だより
大学出張講義2023
-
進路指導室だより
令和6年度 大学入学共通テスト 出願
-
進路指導室だより
卒業生からのメッセージ 2
- 全ての記事を見る
-
図書館だより
【コラボ企画】三田市立図書館展示棚2024年3~5月の展示「中学生になってから読んだ本」
-
図書館だより
防災コーナーに県立図書館の本が加わりました
-
図書館だより
【コラボ企画】三田市立図書館展示棚2024年2・3月の展示「音楽」
-
図書館だより
記念図書館での小さな出来事 ~鳥編~
-
図書館だより
今年も図書委員は文化祭に参加しています
- 全ての記事を見る
イベント情報
-
中学校イベント
5月25日(土)中学オープンスクール〈6年生向け〉【要予約】
-
中学校イベント
5月18日(土)中学オープンスクール 〈4,5年生向け〉【要予約】
-
中学校イベント
4月27日(土)【要予約】授業見学&個別相談会
-
中学校イベント
3月31日(日) こでらじゅく(小学校低学年向け)【要予約】
-
中学校イベント
2月25日(日)ミニ説明会・個別相談会【要予約】
- 中学校イベント一覧をみる 高校イベント一覧をみる